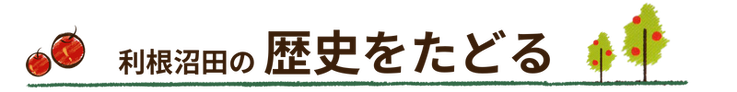- 日本語
- English
- Abbout「Woman Apples School」
- Uncovering Tone-Numata's History
- The Story of Apples in Tone-Numata
- Growing Together Apple Partnerships
- Featured Videos
- Exploring Tone-Numata:An Orchard Guide
- 「Where to Go? Orchard Guide」
- 1.Rinan District, Numata City
- 2.Ikeda District, Numata City
- 3.Sayama District, Numata City
- 4.Shirasawa District, Numata City
- 5.Tsukiyono District, Minakami Town, Tone-gun
- 6.Niiharu District, Minakami Town, Tone-gun
- 7.Kawaba Village District, Tone-gun
- 8.Takayama Village District, Agatsum-gun
- 9.Tone District, Numata City
- 「Farm Etiquette」
- Products & Ordering
- Contact Us
利根沼田が歩んできた時代を少し覗いてみませんか?
この土地の移りゆく風景と、そこに暮らした人々の物語が待っています。
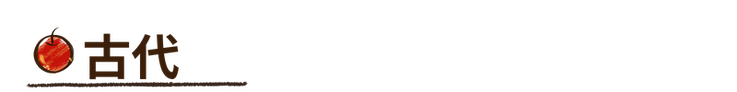
利根沼田地域は縄文時代から人々が定住していたとされ、考古学的な遺跡も発見されています。古墳時代、利根川は交通や物流の要所としても重要で、川沿いの集落を拠点に、人や物資が移動したと考えられます。沼田市内の『奈良古墳群』からは、武器・馬具・装身具等の副葬品が多数発掘されています。

平安、鎌倉時代においては武士の支配が進み、戦国時代には武田と上杉の戦争がこの地域に影響を与えました。沼田城は特に有名で、軍事的な役割を担いました。1554年に武田信玄の軍が沼田城を攻略し、武田家の影響下に入りました。その後、防衛拠点として利用され、北関東への侵攻の足掛かりとしても重要性が増します。信玄の死後、信濃と上野(群馬県)を巡る争いが続きましたが、沼田城はその戦略的な位置から再三にわたり争奪戦が行われ、上杉家の支配下に入りました。その後、戦国大名の真田氏や北条氏が拠点とし、政治・軍事的に重要な役割を果たしました。

江戸時代の初期は真田家がこの地を所領したが、1700年代に入ると本多家が入封し、以降黒田家や土岐家が治め、明治の廃藩置県に至った。江戸時代から明治時代にかけて、利根川の治水事業が進められ、沼田藩の支配下で農業や林業が発展しました。
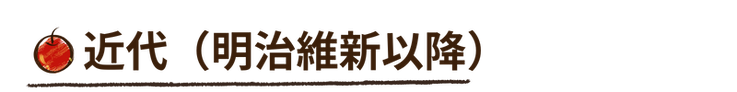
廃藩置県後、この地域は群馬県に編入されました。交通網の整備が進み、農業と林業が引き続き地域経済の基盤を形成しました。1900年代に入ると、利根川流域や尾瀬などの自然を活かした観光業が発展し、地域経済に重要な役割を果たしました。
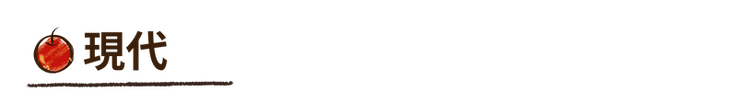
農業の中心地として発展し、現在でもりんごをはじめとする果樹栽培や、利根川上流の清流を活用した観光が地域の特色となっています。農観連携(農業と観光を結びつけた取り組み)や、尾瀬国立公園や三国峠などの自然景勝地を利用したエコツーリズムも注目されています。利根沼田地域の歴史は、古代から現代までの日本の自然と人々の営みの豊かな融合を物語っています。